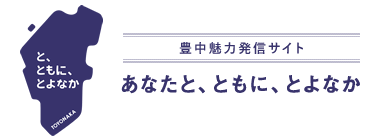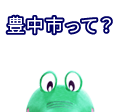豊中ゆかりの人
ページ番号:242508958
更新日:2024年8月26日
渋谷庄三郎 日本人として最初にビール醸造に成功
渋谷庄三郎は文政3年(1820)、大坂の綿問屋「桜井屋」に生まれました。この桜井屋は、寛保元年(1741)に豊中・桜井谷出身の渋谷家が開いたもので、桜井谷の野畑春日神社の神官を代々務めた家系にあたります。幕末には、大坂の五大綿問屋に数えられ、庄三郎はその経営をはじめ、清酒醸造や海運など多角経営を行い、明治初期に官立の通商会社の頭取となります。同社がめざした麦酒製造が頓挫すると、その計画を引き継ぎ、日本人番頭に外国人技師から製造技術を習得させて、堂島に所有する蔵を改造した「渋谷ビール製造所」でビールの醸造を始めました。
しかし、当時はまだ一般の人々にビールの味が受け入れられず、価格も高価であったことから、売り上げは十分ではなかったようです。渋谷ビール製造所は明治14年(1881)にビールの醸造を中止しますが、これが先駆けとなり、その後明治20年前後に、現在の大手ビール会社の前身となる麦酒醸造会社が成立していきました。
(「新修豊中市史 第8巻 社会経済」より)


西村真琴 豊中の社会教育の基礎を築く
マリモの研究者、人造人間(=ロボット)の作製者として知られる西村真琴(1883-1956)は、長野県に生まれ、昭和2年(1927年)に北海道帝国大学教授から大阪毎日新聞社入社を機に、現在の豊中市に居住地を移します。昭和22年(1947年)に豊中市議会議員に当選し第5代議長を務め、その後、豊中市立公民館(現在の中央公民館)の館長として文化・芸術分野などに多くの足跡を残しています。
西村にまつわるエピソードとして、中国の文学者・魯迅との交流があります。昭和7年(1932年)の上海事変直後、三義里というまちを訪れた際に、一羽の鳩を保護します。「日本の鳩との間に子鳩が生まれたら、平和の使者として上海に送ろう」と考え、自宅に連れ帰り、三義と名付けて飼っていました。しかし、鳩は死に、同情した村の人たちが庭先に野面石を持ち込んで塚を立て、亡骸を埋めました。西村が鳩の絵に日中友好の思いを込めた短歌を添えて魯迅に贈ったところ、感激した魯迅から七言律詩が贈り届けられました。
その塚は「三義塚」と呼ばれ、昭和61年(1986年)に豊中市制50周年を記念して、ゆかりの深い豊中市立中央公民館に移されました。
(「新修豊中市史 第11巻 社会教育」および中央公民館設置の説明板より)

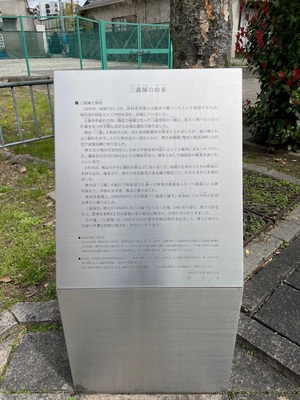
手塚治虫 漫画家・アニメ作家として活躍
手塚治虫(1928-1989)は、昭和3年に現在の豊中市に生まれ、昭和8年に宝塚に移住するまでの5年間を豊中で過ごしています。
昭和 63年(1988年)10月に豊中市立第三中学校を訪れた際に、1枚の色紙に絵を描き生徒たちにプレゼントしました。その絵をもとに制作された銅版パネルが、豊中市すこやかプラザの2階に展示されています。
豊中ゆかりの人によるエッセー
学術や文化、スポーツ、芸能など、さまざまな分野で活躍する皆さんから、「広報とよなか」にご寄稿いただいたエッセーが、平成23年(2011年)の市制施行75周年記念冊子「豊中リレーエッセー ゆめ・まち・ひと」にまとめられています。豊中市立図書館でご覧いただけます。
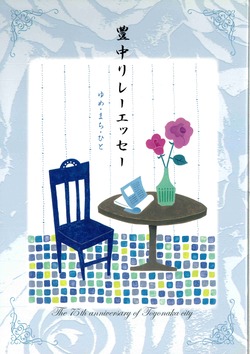
お問合せ
都市活力部 魅力文化創造課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2503
ファクス:06-6858-3864