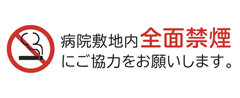豆知識【脳神経内科】:頭痛のはなし
ページ番号:185339581
更新日:2024年12月25日
頭痛は、ほとんどの人が経験する一般的な症状です。紀元前3000年のバビロニアの古代文献にも片頭痛の記載があり、この病気はその頃から人々の「頭痛の種」だったようです。現在、我が国の頭痛人口は3000万人とも言われています。そのすべての人が治療を必要とするわけではありませんが、生活に最も支障をきたす病気の一つです。

頭痛は大きく3種類に分けられます。二日酔いや風邪による頭痛は、原因がなくなれば軽快します。特に問題となるのは一次性頭痛と二次性頭痛です。二次性頭痛とは、病気の症状の一部として起こるもので、クモ膜下出血や髄膜炎など放置すると生命に関わるものなども含まれます。これまで経験したことがないほど激しい頭痛だったり、症状がどんどんひどくなる、吐き気、高熱を伴うような時は、二次性の「こわい頭痛」を疑う必要があります。
原因となる病気がないのに繰り返し起こる頭痛は、一次性頭痛と呼ばれます。いわゆる慢性頭痛で、頭痛の中で最も多いタイプです。これには片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛があります。慢性頭痛では、たとえば頭を冷やすのか体を温めるのか、運動するのか安静が良いのかなど、そのタイプによって対処法が異なるため、自分の頭痛のタイプを知ることが大切です。緊張型頭痛が最も多く、半数以上を占めます。首や肩のこりを伴うことが多く、長時間のデスクワークや姿勢の悪さ、精神的ストレスなども原因になります。
次に多いのが片頭痛で、その数は800万人とも言われています。三叉神経と血管の刺激が痛みの発生に関係していると考えられています。誘因には個人差があり、ストレス、睡眠不足、過労、アルコール、食品、人ごみ、騒音、月経など様々です。日常生活を工夫することにより、これらの誘発因子を取り除き、片頭痛の頻度や痛みの程度を減らすことができます。薬の使い方についてですが、軽症では市販薬でも対応可能です。しかし生活に支障をきたすほどの痛みでは、市販薬の効果がなければ漫然と使い続けることなく、医療機関を受診して適切な治療や効果的な薬に変える必要があります。病院で処方される薬には、鎮痛薬の他に、頭痛を起こりにくくする予防薬やトリプタンという片頭痛の治療薬があります。現在も新しい薬が研究・開発されています。
日常生活に支障があったり、いつもと違う頭痛を経験した時は、医療機関で相談するようにしましょう。「たかが頭痛くらいで病院へいくことはない」と考えて、かえって頭痛を悪化させてしまうこともあります。我慢しないことが、頭痛治療の近道かもしれませんね。