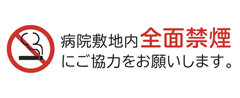医療安全管理指針
ページ番号:360293354
更新日:2025年7月31日
目次
第1 趣旨
この指針は、市立豊中病院(以下「本院」という)における医療事故の発生防止対策及び医療事故発生時の対応方法について、本院が取り組む際の指針を示すことにより、医療安全管理体制の確立を促進し、安全で質の高い医療の提供に資することを目的とする。
第2 基本的な考え方
本院は、豊中市の地域中核病院として「心温かな信頼される医療」を提供することを基本理念に掲げ、その実現に向け以下のとおり実施していく。
1.医療安全の確保
患者の安全を第一に考え、その対策として医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と施設全体の組織的な事故防止対策の両面から医療安全の確保を推進する。また、事故発生時には速やかに対応し、患者の被害を最小限に食い止めるよう努力しなければならない。
2.医療における信頼の確保
本院では患者の権利を明文化しており、患者を中心にした医療の提供を行うべく尽力しているところである。そのために患者の要望に真摯に耳を傾け、患者が納得するまで話し合うことにより、患者が自らの意思で治療方法などを決定できるよう努めなければならない。また、患者自身からの情報の開示請求に対しても積極的に応じていく。
第3 用語の定義
1.インシデント
患者の診療やケアにおいて、本来のあるべき姿からはずれた行為や事態の発生、また患者だけではなく訪問者や医療従事者に傷害の発生した事例や、傷害をもたらす可能性があったと考えられる状況をいう。
2.アクシデント
有害事象とされ、疾病そのものではなく医療を通じて患者に発生した障害を意味し合併症、偶発症、不可抗力によるものも含まれる。これらは「過失によるもの」「過失によらないもの」に大別され、前者も再発防止の対象となる。
3.医療過誤
「患者に障害があること」「医療行為に過失があること」「患者の障害と過失間に因果関係があること」の3要件が揃った事態を意味する。
第4 医療安全管理体制
1.医療安全管理委員会の設置
医療安全管理委員会設置要綱に基づき、医療安全管理委員会を設置し、本院における医療上の安全対策の推進など、安全管理体制の充実を図る。
医療事故発生時には必要に応じて事故調査会を設置し、事故の原因究明と対応について検討する。
2.医療安全管理室の設置
院内での医療安全管理業務を統括・調整する部署として医療安全管理室を設置し、専従の医療安全管理者及び職員並びに兼任の職員を配置し、医療安全管理委員会と連携して活動を行う。
3.セフティマネジャー組織
現場で発生したインシデント等を迅速に把握するために、部署ごとにセフティマネジャーを任命し、その対応や当事者への指導を行う。また、医療安全管理委員長の下にセフティマネジャー全体会議を開催し、組織的な医療事故防止対策を構築して実行する。なお、セフティマネジャーが長期に及ぶ不在となる場合には、当該セフティマネジャーが所属する部署の長が代理を選任し、医療安全管理委員会に報告、承認を受ける。
4.チーフセフティマネジャー組織
報告のあったインシデント等について、多職種において内容の調査・分析と対策の立案及び実行の確認、評価、必要に応じてセフティマネジャーに対して助言、指導を行うため、各部門にチーフセフティマネジャーを任命する。
チーフセフティマネジャーは、医務局、中央診療局、薬剤部、看護部、事務局等の各部門から選任されたもので構成し、再発防止対策の浸透、再発予防のための活動を行う。なお、チーフセフティマネジャーが長期に及ぶ不在となる場合には、医療安全管理委員会委員長が、当該チーフセフティマネジャーが所属する部門の長と協議のうえ代理を選任し、医療安全管理委員会に報告する。
第5 医療安全管理のための具体的方法
1.医療安全管理マニュアルの策定等
安全で質の高い医療を提供するために、医療従事者として守るべき基本的な義務を記載したマニュアルを策定する。また、院内各種マニュアル等の策定及び改定時にあたっては、医療安全管理体制における他職種との連携を活かし、各専門分野から医療安全にかかる確認を行う。
2.インシデントレポートの集約及び分析、フィードバック
医療安全管理マニュアルに基づいて報告されたレポートを医療安全管理室で集約し、分析結果をフィードバックすることで医療の質向上を図る。
そのための人的・物的環境の整備を構築していく。
3.医療ADRの構築
患者を中心とした医療を提供していく中で、増加する医事紛争を裁判外で迅速に解決できるような制度の整備を図る。
4.職員研修
医療安全管理に対する意識を高めるため、年2回の職員研修を開催する。
5.医療安全に係る評価
複数の医療機関が連携し、直接赴きチェックシートに沿って互いに医療安全対策に関する評価を行う。
第6 医療事故発生時の対応
患者の生命を第一に考え、関係職員は下記のことにつき、迅速かつ正確に行動しなければならない。
(1)患者の応急処置
(2)家族及び上司(病院長)への連絡
(3)患者家族等への説明
(4)正確な記録の作成
(5)証拠の保全と原因究明への努力
(6)当事者に対する配慮
また、医療の透明性を高め、公的病院として市民等に説明責任を果たすこと、事故の再発防止を図ることを目的として、「医療事故等の公表に関するガイドライン」に則して公表を行う。
第7 患者からの相談への対応
病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、 担当者は必要に応じ主治医、担当看護師等関係部署へ内容を報告する。
第8 指針の閲覧に関する基本方針
本指針については、市立豊中病院のホームページに掲載し一般に開示する。また、患者家族等から閲覧の求めがあった場合は、これに応じるものとする。
第9 その他
職員は本指針の目的を十分に理解し、本院の医療安全活動に積極的に参画するよう努めなければならない。
附則 この指針は、平成18年5月1日から適用する。
附則 この指針は、平成20年4月18日から適用する。
附則 この指針は、平成29年12月1日から適用する。
附則 この指針は、平成30年10月1日から適用する。
附則 この指針は、令和元年7月1日から適用する。
附則 この指針は、令和3年1月1日から適用する。
附則 この指針は、令和7年5月16日から適用する。