人権の大切さを考えよう~当たり前の生活を送るために~
ページ番号:822430986
更新日:2025年11月10日
人権は、憲法で保障されている そもそも、憲法ってなに?
監修・解説:大阪弁護士会所属 塩見拓人弁護士
憲法とは、国家が「やってはいけないこと」や「やるべきこと」
といったことを国民が定めた決まりです。
憲法が機能しないと国家が無秩序に人権を侵害してしまうこととなるため、
国民を守るべき大事な存在が憲法となります。
日本国憲法 e-Gov法令検索 (外部リンク)
※e-Gov法令検索とは、デジタル庁がウェブサイト上で提供する日本の法令の検索・閲覧システムです。
憲法で保障されている人権について以下のケースを使って考えてみましょう
- ケース1【SNSの脅威】
- ケース2【被疑者・被告人の弁護】
- ケース3【夢への一歩】
- 裁判例1【被差別部落の部落名等を載せた書籍の販売の禁止等を求めた民事裁判例】
- 裁判例2【SNSでの誹謗中傷による民事裁判例】
- 裁判例3【障害者に対する差別的表現に対しての民事裁判例】
- 裁判例4【外国人に対する差別的表現に対しての民事裁判例】
ケース1【SNSの脅威(SNSに自分の考えや写真など自由に投稿してもいいの?)】

事例
ある日、Aさんが雑誌を読んでいたところ、Aさんが大ファンのある作家の新冊に関し、
評論家のBさんが、「昔の勢いが感じられない駄作であり、読んだ時間を返してほしい。」と批評していました。
Bさんの批評に怒ったAさんは、SNSの公開アカウントにて、
「Bは評論家もどきであって、賄賂をもらって批評をするポンコツである。Bの批評は一切参考にならない。」
と投稿したところ、Aさんの投稿は瞬く間に拡散されることとなりました。
なお、Bさんが誰かから賄賂をもらったという事実は一切ありません。
考えてみよう
AさんのSNSでの投稿は法的に問題があるでしょうか。
また、Bさんのある作家の新冊に対する批評についは、問題はないのでしょうか。
憲法の規律
SNSに自分の考えや写真を投稿することは、憲法21条の「表現の自由」として保障されています。
しかし、無制限に表現の自由が保障されているわけではなく、他の権利との調整が必要となります。
例えば、他人の名誉を毀損(きそん)したり、プライバシーを侵害したりする投稿は、
不法行為(民法第709条)や名誉毀損罪(刑法第230条)に該当し、違法となる可能性があります。
解説
Aさんの投稿はBさんの社会的評価を下げる投稿であり、ましてやそれが虚偽の内容である以上、
表現の自由として保障される範囲を逸脱しており、違法となる(Bさんから損害賠償請求される)可能性が高いです。
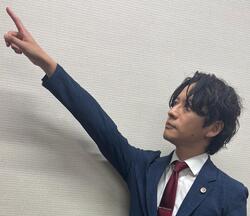
ココがポイント!
憲法が保障されている権利も他の権利との調整で成り立っていて、無制限に保障されるものではなく、
バランスが非常に重要となってきます。
ケース2【被疑者・被告人の弁護(罪を犯した人に弁護士がついて弁護してもらえるのはなぜなの?)】

事例
Cさんは仕事の過労で睡眠不足状態が続いており、運転の際に前方不注意で赤信号に気付かずに交差点内に侵入し、
青信号を守って横断歩道を歩いて渡っていた小学生をひいて、大けがをさせてしまいました。
Cさんはその場で警察官に逮捕され、警察署で勾留されていたところ、
弁護士が訪れ「あなたの刑事弁護をつとめることとなりました。よろしくお願いします。」とあいさつされました。
考えてみよう
被疑者・被告人であるCさんに弁護士がつくのはなぜでしょうか。
憲法の規律
憲法34条、同37条3項は、すべての被疑者・被告人に対し、弁護人を選任する権利を保障しています。
被疑者・被告人は、警察や検察官と比べて、法律に関する専門的知識も証拠の収集能力も圧倒的に劣っています。
訴訟当事者間の対等性を確保し、被疑者・被告人の防御権(逮捕された人が自分自身を守るために認められた権利)を保障するためには、
専門的知識を備えた法律家の援助が不可欠です。
そのため、憲法は被疑者・被告人に弁護人を選任する権利を保障しているのです。
刑法は刑罰法規(例えば懲役3年等)を定めていますが、被疑者・被告人に対し、刑罰を科すにしても刑事裁判を行う必要があります。
その手続きを適正に行うためにも、弁護士による援助が必要となります。
解説
Cさんが犯した罪はCさんが償う必要があります。
しかし、Cさんにも情状酌量(じょうじょうしゃくりょう)の余地があり(過労)、
被害者の方との示談や今後のCさんの反省(例えば仕事を変えたり、今後はCさん以外の家族が運転したり等)、
更生の余地を見つけるためにも、弁護士の力が必要不可欠となるのです。
ココがポイント!
弁護士は被疑者・被告人の弁護をしますが、それは刑事裁判が適正な手続きを経て、
適正な刑事罰(無罪を含む)を科すことを目的としており、その適正手続きを確保するために弁護活動を行っています。
ケース3【夢への一歩(どんな仕事をするか自分で決めていいの?)】

事例
高校生のDさんは、高校を卒業したら起業しようと考えていました。
しかし、Dさんの親から「大学に行かず、起業するのは許さない。必ず大学に行っていい会社に勤めなさい。」
と言われ、大げんかになりました。

考えてみよう
Dさんは親の言うことを聞いて、大学に行き、いい会社に就職しなければならないのでしょうか。
憲法の規律
どんな仕事をするか、どのような職業に就くかは、職業選択の自由として、憲法22条1項により保障されています。
職業選択の自由は、個人の人格的価値や自己実現と深く結びつく重要な権利と位置付けられています。
そのため、誰もが自分の職業を自由に決定することができます。
解説
Dさんは、自分の生き方を自分で決める権利があり、大学へ行かず起業することが可能です。
なお、大学へ行きながら起業するなどの方法もあり、親と話し合うことも大事なことです。
ココがポイント!
憲法が保障するものの中に、自己実現のための権利も存在します。
誰もが幸福を追求し、尊厳を確保することも、憲法の重要な側面の1つです。
人権が問題になった裁判例
1..被差別部落の部落名等を載せた書籍の販売の禁止等を求めた民事裁判例
【事案の概要】
全国の被差別部落の部落名や現在地などを一覧表にして書籍を出版しようとし、同書籍の電子データや個人の住所、電話番号、SNSのアドレスなどの個人情報を承諾なくインターネット上に開示しダウンロード可能な状態においた被告に対して、原告らが同情報の削除や出版の禁止、損害賠償請求などを求めて訴訟を提起した。
【判決】
人は誰しも不当な差別を受けず、尊厳を保って平穏な生活を送る人格的利益があり、被差別部落出身と推測できる情報の公表は当該利益を侵害するとして、31都道府 県分についての出版禁止、インターネット上の情報の削除及び損害賠償請求を認めた(東京高等裁判所令和5年6月28日)
【関係する人権】
幸福追求権(憲法13条)、平等権(憲法14条)、表現の自由(憲法21条)
【塩見弁護士のコメント】
「知られたくない権利」も憲法で保障されている権利であり、部落差別を違法とみなした重要な裁判例です。
2.SNSでの誹謗中傷による民事裁判例
【事案の概要】
テレビ番組に出演していた女性がSNSでの誹謗中傷を苦に自殺した後、
SNS上でとある男性が「あんたの死でみんな幸せになったよ、ありがとう」、
「(番組名)楽しみにしていたのにお前の自殺のせいで中止。最後まで迷惑かけて何様?地獄に落ちなよ」と投稿した。
【判決】
約129万円の支払を命じる判決(東京地方裁判所令和3年5月19日)
【関係する人権】
人格権(憲法13条)、表現の自由(憲法21条)
【塩見弁護士のコメント】
テレビ番組の感想と言えど、表現の自由での保護には限界があります。言葉の暴力の違法性を認めた点で、意義のある裁判例です。
3.障害者に対する差別的表現に対しての民事裁判例
【事案の概要】
難病により左手以外を動かせない障害者に対して、ネット掲示板で「生かしておく理由が無いなあ。一思いに殺してやれよ」と投稿した。
【判決】
本件投稿は、原告の生存する意義及び人格的利益を否定する趣旨のものであって、社会通念上許容される限度を超える侮辱行為であり、被告が本件投稿をしたことによって、原告の名誉感情が侵害されたと認められ、不法行為が成立するとしたうえで、本件投稿が原告の生存する意義及び人格的利益を否定する趣旨のものであること、本件投稿が障害者を差別するヘイトスピーチに該当するものであること等を考慮して、慰謝料50万円の損害賠償を命じる判決(前橋地方裁判所令和6年1月24日判決)
【関係する人権】
平等権(憲法14条)、表現の自由(憲法21条)
【塩見弁護士のコメント】
障害者にも当然憲法により人権は保障されています。近年めだつヘイトスピーチの違法性にも着目した意義のある裁判例です。
4.外国人に対する差別的表現に対しての民事裁判例
【事案の概要】
原告(外国人)の「外国人が住みよい社会になってこそ、日本人も暮らしやすくなる」との発言が掲載された記事を、自身が開設したブログ内で引用したうえで、「なにが、『外国人が住みよい社会になってこそ、日本人も暮らしやすくなる』だ!日本国は我々日本人のものであり、お前らのものじゃない!『外国人が住みよい社会』なんて、まっぴらごめんだし、そんな社会は作らせない。思い上がるのもいい加減にしろ、日本国に
【判決】
「日本国に
【関係する人権】
人格権(憲法13条)、平等権(憲法14条)、表現の自由(憲法21条)、居住の自由(憲法22条)
【塩見弁護士のコメント】
外国人の方にも一定の制約はあるものの、日本国内においては憲法により人権は保障されています。
これから外国人との問題も増えかねない現代社会において、その関わり方にも警鐘を鳴らす重要な裁判例です。

最後に
私たちが人間らしく幸せに生きるために、基本的人権の尊重が、日本国憲法によって保障されています。
人権は、私たちが当たり前だと感じている日々の生活を支えている大切なものです。
上記のケース以外にどのようなことが保障されているのかなど、興味をもってもらえれば幸いです。




