こころの病の体験を社会に役立ててみませんか?プロジェクト
ページ番号:580759004
更新日:2025年12月15日
こころの病の体験を社会に役立ててみませんか?プロジェクトとは
こころの病をもつ人の中には、例えば「病気を理解してもらうために自らの体験を伝えたい」「何か社会の役に立ちたい」と思っている人がたくさんおられます。
でも、「うまく話せるか自信がない」「役立つといっても自分になにができるのだろう?」などと、あきらめている人も多いのではないでしょうか。本市ではそういった「こころの病を体験した自分を生かしてみたい。活躍したい」という人のために、体験の役立て方を学び、あなた(こころの病の体験者)にふさわしい活躍の場を仲間とともに探すプロジェクトを平成24年度から実施しています。
こころの病の体験の「価値」に気づき、社会に役立てることで、自身のリカバリー(回復)も目指すこのプロジェクトにご参加いただき、こころの病の有無にかかわらず、より暮らしやすい社会をめざし、力をあわせて取り組むことができれば・・と考え企画されているプロジェクトです。

今後このプロジェクトがどのように発展していくのかは、参加される皆さんと話あいながら夢を膨らませていければと考えています。
植物に例えるならば、このプロジェクト、今は「種」の段階。
「こころの病の体験を社会に役立てる」ことを目標に、当事者、スタッフがともにこの種に水をあげ、日光にあて、肥料をあげて、育てていきましょう。どんな花が咲くのか、どんな実をつけるのか・・楽しみですね。
プロジェクト講師 泉 洋一 先生にお聞きしました
平成24年度から講師をしていただいている佛教大学の泉洋一先生にこのプロジェクトのことをお聞きしました。
※令和6年度に「こころの病の体験を社会に役立てよう!プロジェクト」から「こころの病の体験を社会に役立ててみませんか?プロジェクト」に
事業名を変更しました。
体験を社会に役立てるってどんなこと?
「病の体験を社会に役立てよう! プロジェクト」ということで豊中市では平成24年度から実施しているのですが、そもそも、「病の体験を社会に役立てる」とか「リカバリー」と聞いても、まだまだ知られてないことなので、イメージのわかない方も多いのではないかと思います。そこでまず、先生にお聞きしたいのですが、こういった「体験を社会に役立てる」といった取り組みは最近取り組まれてきたことですか。

<泉先生>
体験を語って、社会に役立てるというのは、精神障がいに限らず、いろいろな領域でされてきました。例えば、第二次世界大戦下のナチス強制収容所の体験を書いたフランクルの「夜と霧」や「奇跡の人」の映画にもなったヘレン・ケラーが知られています。この二人は、世界中を巡って自身の体験を語り、啓発活動をしていたこともあげられます。
フランクルは、悲惨で過酷な状況を生きのびて、人が生きる意味をその体験から問いかけ、苦境や絶望のなかでも希望を見出せる人間のこころの気高さを訴えました。また、ヘレン・ケラーは、自らの障がいを受けとめ、勇気をもって社会とつながることで、どのような障害があろうとも人は人の役に立つことができるという、人間の根源的な存在価値を伝えた人です。このように自身の体験を社会に伝えることで世の中が変わってきた部分というのはあります。

インタビュアー
そういわれてみれば、学生の頃、戦争の歴史を伝える資料館のようなところに行ったときに、戦争体験をした人から体験談を聞いたとき、リアリティがあってすごく伝わってきたということを思い出します。
そういった大変な経験をした人にしか伝えられないものがある、その体験そのものに価値があるということになるのですね。
「体験をしていない人に伝える」ということも、その体験をした人にしかできない、かけがいのないことですが、それとは別に、同じような体験をした人同士が体験を「語り合う」というのも、精神保健の領域ではよく聞きますね。

同じ病の体験を持った人が集まって体験を語るというのは、歴史的には20世紀の半ば頃から始まったと言われています。例えばアルコール関連問題の分野では、AA(アルコホリックスアノニマス)というアルコール依存症の人たちのセルフヘルプグループが有名です。その始まりは1935年と言われていますが、いまは世界160以上の国で飲酒に伴う様々な体験を語り合うグループが広がり、依存症からの脱却とリカバリー(回復)に役立っています。

また、精神科病院でのセルフヘルプグループの取り組みをきっかけに退院した精神障がい者の集まりを発祥とする「クラブハウスモデル」も「リカバリー」と関係が深い活動です。クラブハウスモデルでは、精神障がい者が会員(メンバー)となり、スタッフとともにクラブを主体的に運営する過程で働く力を取り戻したり、社会的な役割を見いだしていきます。1948年にアメリカのニューヨークで始まった心理社会的リハビリテーションの取り組みです。精神疾患を持つ当事者がクラブハウスを利用し、仲間との支え合いのなかで自尊心や自己肯定感を取り戻し、自分の長所や健康な側面を伸ばすことで、社会に貢献する力を取り戻します。その過程をリカバリーと言います。
リカバリーとは?

そのリカバリーという概念について、もう少し詳しくご紹介いただけますか。

まず精神疾患を持つ当事者が自分の体験を手記にして出版し、社会に大きな影響を与え、精神衛生(今日では精神保健福祉)と言う言葉を生み出したのが1908年のことです。その後、AAを代表とするセルフヘルプグループの活動やクラブハウスモデルの取り組みが生まれ、自らの体験を仲間と共有し、社会に伝えることを通じて、生きる意味を見いだしてきました。
また、その活動の過程で病気や障がいの治癒や回復という体験だけでなく、病気や障がいを持ちながら生活をすることの意味、そしてそれらを乗り越えて社会のなかで自分自身の人生の目標や働く力を獲得し、多くの精神障がい者が社会復帰・社会参加を成し遂げていったのです。
このような取り組みを経て、1980年代にリカバリーという言葉と概念が、精神疾患を持つ当事者の手記の公開を機にアメリカで普及していきました。いまやリカバリーは、欧米においてノーマライゼーションやソーシャル・インクルージョンなどの福祉政策の理念と同様に、精神保健福祉の最も重要な政策に位置づけられています。

なお、リカバリーには様々な定義があるのですが、例えばマーク・レーガンという人は次のように説明しています。
「統合失調症などの重い精神の病をもっていても、人は立ち直ることができます。人として尊重され、希望を取り戻し、社会に生活し、自分の目標に向かって挑戦しながら、かけがえのない人生を歩むこと、それが「リカバリー」です」
また、ある精神障がい当事者の体験談では、リカバリーを次のように語っています。
「病気や障害があることではなく、無力感、希望のなさ、自尊心喪失こそが問題なのである。人生を取り戻そうとしている過程こそがリカバリーである」

リカバリーというのは、病気があっても自分の希望や自尊心を取り戻し、自らの生活や人生に挑戦する「過程」と言う意味なのですね。
ありがとうございました。
グループ名「心音(こころね)」とロゴマーク

心音ロゴマーク
グループ名の「心音(こころね)」は、「こころの動きや揺れを音符でイメージし、左右に揺れながら休符も入れ、メンバーそれぞれの音で音楽を奏でる」という意味を込めています。
ロゴマークのテーマは「休もう」。
こころが疲れた鳥がとまり、周りは虹でもあり、音符が活躍する五線譜でもあります。
体験談による啓発活動を行っています
心音では、こころの病の啓発活動として、体験談をお話ししています。
大阪府立豊島高校で人権学習の講師をしました。
平成27年度よりほぼ毎年、大阪府立豊島高校のテーマ別人権学習「精神障がいについて考える」の講師をしています。
体験談を通して、高校生へ「こころの病は身近な病気であること」、「しんどい時は一人で抱え込まないこと」などをメッセージとして伝えています。
毎年、生徒一人一人からお礼の手紙をいただくので、メンバーにとって励みになっています。
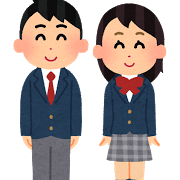
お礼の手紙より
- 今までは、こころが弱いからうつ病になると思っていたけど、お話を聞いて、ちゃんとした病気であることを知って、考えが変わりました。
- 4人に1人がこころの病になることを知り、自分もかかる可能性があることが分かりました。その時は迷わず保健所や友達に相談しようと思いました。そして、自分も友達の相談に乗り、手助けしようと思いました。
- 今後、自分の周りの人、または自分自身がこころの病になった場合、どのように向き合っていけばいいのか、どこに相談すればよいのかも含めて、参考となる話を多く聞くことができました。

メンバーの声
とても緊張したけれど、講師にチャレンジして良かったです。病と向き合うことの効果を実感することもできました。今回の経験を通して、こころの病はマイナス面もあるけど、いろんなことに気づかせてくれる歯車のようだと感じることができました。
他にも、市民や支援機関向けの講座などの講師依頼を受け、活動しています。
第1回 プロジェクトの活動報告 短縮版
第1回 プロジェクトの活動を一部抜粋したものです。
プロジェクト参加者の声
現在は躁うつ病、不安神経症、社交不安障害、統合失調症等の方が参加されています

参加者Aさん
『私はこのリカバリープロジェクトに参加し、価値の変換という事を学びました。病気を通して価値が変わったりしました。
20歳の時に発病して、20代は真っ暗でしたが、地道に自分のお医者さん(自分の病気のことをお医者さんや友達に相談して、アドバイスをもらい、自分の病気を研究する)になって、今はかなり落ち着いています。病気になって沢山の事を学びました。』

参加者Bさん
『リカバリープロジェクトに参加して、1番に思うことはホッとしたことです。社会に役に立ちたいと気負って参加しましたが、頑張らなくても、病気があっても、症状が出ることがあっても、私にできることがあるかも知れないと知り、すごくホッとしました。
ありのままの自分でいい、と言われているようで嬉しくなりました。
4日間の講座終了後も月に一度集まり、病気について分かち合ったり、病気の経験を社会に生かす方法を考えたり、また病気を持っていても自立して暮らしていける社会の将来像を話したり、すごく有意義な時間です。居場所も感じ、社会に参加している実感も持つことができました。メンバーが増え、新たな輪が広がったらいいなと思っています。』

参加者Cさん
『市の広報を見て、興味を持ち「リカバリープロジェクト」に参加しました。養成セミナーを終了したら、「何か」を直に始められるのかとおもっていたのですが、そうではなく「何か」を考えることからスタートでした。
月1回のミーティングでは、「こころの病の体験を社会に役立てる」ことの話し合いを軸に、自分自身の病への気づき、見つめ直しができました。今回、セミナー参加者の方も、私たちと一緒に心の声を言葉にして、一緒に前にすすみませんか?』

参加者Dさん
『わたしは作業所(福祉サービス事業所)でポスターを見て、リカバリープロジェクトに参加しました。今まで、私は大学や専門学校で体験談を語ってきました。さらに良い「病の体験の社会への役立て方」が学べるかもしれないと思い、参加した次第です。
リカバリーは回復という意味ですが、薬をやめなくても、病気が完治しなくてもリカバリーが可能だと分かりました。リカバリーとは、希望や自尊心を持っていく過程、自分らしく生きていくことです。
リカバリープロジェクトでは、4回の講座終了後も月1回くらいのペースで集まり、近況やリカバリーについて話し合いました。新しい仲間ができてとてもよかったです。これからも一緒に活動していきたいです。
みなさんもわたしたちの輪に加わりませんか?』

参加者Eさん
『きっかけは、広報の中に≪病の体験を社会に役立てよう≫の一文を見たからです。
6年間の投薬治療後、自身をコントロールできるまでになり、「私の経験が少しでも世の中で活かせないだろうかと…」と思い続けていました。月一回、保健所に足を運ぶたび思うのは、参加しているみんなの顔を見ることができると、「今月も、顔を見ることができて良かった~」、お休みされる方がいると逆に「どうしているのかな?」と、心配になったりしています。病院の先生や家族や友人とはまた違う・・・なんでしょうか?病を体験した人ならではの優しさを持っている方がいてくれることで、安心しているのでしょうね。まだまだ、これから・・・ボチボチ何かを形にしたいと思いながらの場所ですが、病の体験が活かせるきっかけ作り、一緒に参加できる方が増えると良いな~って思っています。』

参加者Fさん
『以前は、病気になったことを後ろめたく思っていました。必ず治さなければいけないものと思っていました。(そう思えば思うほど、苦しくなっていました。)リカバリープロジェクトに参加して、病気のままでも、治らなくても私にできることがあると知りました。今は「何もかわらなくていい、あなたはあなたのままでいい。」と同じ病をもつ仲間に伝えたいです。』
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問合せ
健康医療部 医療支援課 精神保健係
〒561-0081 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7315
ファクス:06-6152-7328




