成年後見制度(法定後見制度)
ページ番号:456369673
更新日:2025年2月4日
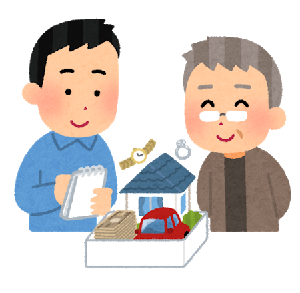
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、本人の意思決定を尊重しながら支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、判断能力が不十分になった後に家庭裁判所に申立てることにより、成年後見人等を選任してもらう「法定後見制度」と、判断能力が十分なうちに判断能力が不十分になったときに備え任意後見人を自分で選び契約しておく「任意後見制度」があります。
任意後見制度やその他の財産管理に関する契約サービス(日常生活自立支援事業、財産管理委任契約等)については、下の「成年後見制度等」からご確認ください。
法定後見制度とは?
法定後見制度とは、すでに判断能力が十分でない方のために成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)を選任し、本人の意思を尊重しながら財産管理や身上監護を行い、本人の生活や権利を保護・支援する制度です。制度を利用するには、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれており、判断能力の程度などに応じて制度を選べるようになっています。
| 類型 | 対象となる人 | 援助者 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力が欠けている のが通常の状態の人 |
成年後見人 |
| 保佐 | 判断能力が著しく 不十分な人 |
保佐人 |
| 補助 | 判断能力が不十分な人 |
補助人 |
成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)とは?

本人の生活・医療・介護・福祉など、自分で判断することが難しい本人の意見や気持ちを聞いたうえで、身の回りに目を配りながら以下のような行為で本人を保護・支援します。
成年後見人等は、家庭裁判所により、本人の親族、法律・福祉の専門職や法律または福祉に関する法人等が選任されます。
法定後見制度を利用すると、本人が自分でできることに応じて、家庭裁判所が「成年後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかを選任します。
| 援助者 | 成年後見人等ができる行為 |
|---|---|
| 成年後見人 | 代理・取消(原則として、すべての法律行為) |
保佐人 |
同意・取消(借金や訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など(民法13条第1項記載行為、その他申立てにより裁判所が定める行為) |
| 補助人 | 同意・取消(申立てにより裁判所が定める行為(本人の同意が必要です。)) |
「代理」…役所や銀行の手続き、福祉サービスの契約などを代わりに行ってくれます。
「同意」…本人が自分で契約などを行うときに、契約内容や財産状況を考慮し、同意を与えることにより判断のサポートを行います。
「取消」…成年後見人等の同意を得ないでした不利益な契約などを取り消すことができます。
※職務は財産管理や契約の法律行為に関するものに限られており、食事の世話や日常の買い物、実際の介護などは、職務ではありません。また、どこまでの範囲で代理や取り消しができるかどうかは、申立ての結果、裁判所が決めます。日常の生活の買物は取り消すことができません。
成年後見人等が必要となるのはどのような場合か?
(例)
- 最近同じものを何度も買ってしまったり、難しいことについては理解しにくくなっているが、介護サービスを利用しながら今後も住み慣れた自宅で生活を続けていきたい場合
- 銀行で通帳と印鑑を何度も間違えてしまい、お金をおろすことができない場合
- 高齢となり判断能力が衰えてきたためか、訪問販売で必要もない高額な商品を何度も買ってしまう場合
- 施設に入所したいが、契約行為については難しくて理解しにくくなっている場合
法定後見制度の申立(利用手続き)
| 主な順序 | 内容 |
|---|---|
1. |
管轄の家庭裁判所へ申立て(※豊中市在住の方は、大阪家庭裁判所です。) |
2. |
家庭裁判所による調査(調査官が本人の生活状況、財産状態などを調査します。) |
| 3. | 精神鑑定(本人の精神の状況について医師等が鑑定します。) |
4. |
審判 |
| 5. | 審判の告知と通知 |
6. |
法定後見開始 |
申立てできる人は?
本人、配偶者、4親等内の親族、検察官などです。
※申立てをする親族がいない、または親族が申立てを拒否している場合などは、本人の福祉を図るために市町村長が申立てをすることができます。
市町村長による申立てについてのお問合せ先
・長寿安心課 06-6858-2866
・障害福祉課 06-6858-2224・2746
・福祉事務所 06-6858-2247
申立てには何が必要か?
申立てには、申立書、申立事情説明書、親族関係図、財産目録等の書類のほか、戸籍や住民票、診断書等(各1通)が必要です。
戸籍謄本(全部事項証明書)、住民票、登記されていないことの証明書、診断書は発行から3か月以内のものをご用意ください。
(申立費用:裁判所に納める費用)
収入印紙 |
800円分(※保佐・補助で同意権・代理権付与が加わる場合はその分増額) |
|---|---|
| 収入印紙(登記用) | 2,600円分 |
| 連絡用の郵便切手 | 3,990円分(※詳細は、下記チェック表よりご確認ください) |
| 鑑定費用 | 家庭裁判所が鑑定を必要と判断した場合に発生 |
※ 必要な書類については、以下の「申立てに際してご用意いただく書類等(チェック表)」をご覧いただき、書類がそろっているかご確認ください。
申立てに際してご用意いただく書類等(チェック表)(PDF:213KB)
※ 申立書式については、以下の『裁判所HP「書式ダウンロード(後見等開始・選任申立書式)」』よりダウンロードしていただき、お使いいただけます。
診断書・本人情報シートの作成について
診断書・本人情報シートを作成する際にご利用ください。
裁判所HP「成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引」(外部リンク)
※お困りの際は、以下の豊中市社会福祉協議会 権利擁護・後見サポートセンターにご相談ください。
豊中市社会福祉協議会 権利擁護・後見サポートセンター(成年後見制度等に関する相談窓口)
電話:06-6841-9382
相談内容例:
- 制度や手続きの方法がよくわからない
- 申立てをしたいが、申立人に資産がなく、申立費用等の費用が負担できない
成年後見人等への報酬は必要か?
成年後見人等への報酬を支払うかどうかは、家庭裁判所が決定します。
成年後見人等は、報酬を受け取るために、家庭裁判所へ報酬付与の審判を申し立てなければなりません。報酬は本人の財産の中から支払われるため、本人の資力・成年後見人が管理する財産の内容及び行った事務の内容により、報酬額が決定されます。
成年後見人等の報酬助成
成年後見人等の報酬を支払うことが難しい低所得者の方を対象に、成年後見人等に対する報酬の助成を行っています。
令和2年度までは市町村長による申立てのみ対象でしたが、令和3年度から本人による申立てと、親族による申立てについても対象となりました。
助成対象者
家庭裁判所により後見人等が選任された者で、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、税理士、精神保健福祉士その他親族以外の専門職が後見人等となる者
対象条件
以下のいずれかに該当するもの
- 生活保護受給者
- 次の要件のすべてを満たす者で、後見人等の報酬に要する費用を負担することが困難であると市長が認める者
(ア)対象者及び対象者と生計を一にする世帯員全員が市民税非課税であること。
(イ)対象者の預貯金が500,000円未満であって、かつ、対象者が居住する家屋およびその土地その他日常に必要な資産以外に処分すべき資産がないこと。
要綱
その他の詳細など、申込にあたっては、「地域支援係要綱一覧」より要綱をご確認ください。
※令和3年3月31日までに家庭裁判所の審判により報酬額が決定した場合の助成金は、従前の例「豊中市成年後見人等報酬助成実施要綱(~2021.3.31)」による取扱となります。
成年後見制度に関係する相談窓口
以下の「成年後見制度等に関する相談窓口」から、成年後見制度に関係する相談窓口をご確認いただけます。

よくある質問
よくある質問の回答については、『大阪家庭裁判「よくある質問」』からご確認ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問合せ
福祉部 地域共生課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2219
ファクス:06-6854-4344




